「新年になるし今年は行政書士に挑戦してみたい!でも1月から勉強して間に合うの?」
こんな疑問にお答えします。
行政書士試験は例年11月に行われるので1月から勉強を始めるのなら1年弱の猶予があります。
これは長すぎず短すぎずちょうどいい期間。
勉強を始めるのにまさにちょうどいいタイミングだと言えるでしょう。
では約11ヶ月の間どういう風に勉強をしていけば良いのか?
それは以下をご覧ください。
行政書士の勉強期間の目安は1年

僕も実際に勉強して合格した経験から思いますが、行政書士を受けるにあたり一番良い勉強期間は1年くらいだと思います。(僕は余裕を持って1年2ヶ月)
なぜなら、半年だと時間が足りないし1年を超えてくると間延びして中だるみしてしまうからです。
キリ良く1年で区切って集中して勉強することが一番の近道になります。
そういう意味で言うと1月から11月の試験日までの1年弱という期間はまさにベストなタイミングと言えますね。
行政書士の勉強①まずは憲法を勉強してみよう|2週間~1ヶ月
これまでに何も法律の勉強をしたことがない人はまずは憲法からスタートさせるのが安定です。
憲法は法律の上位にあたる存在ですから、まずここを知らないとダメです。
行政書士の憲法は難しいっちゃ難しいんですけど、しっかり読んでいけば理解しやすいし他の科目に比べて内容もそんなに多くないのでおすすめです。
配点もそこそこ大きいので勉強して損はない科目。
憲法の勉強はだいたい2週間~1ヶ月くらいを目安にすると良いかもしれません。
最初の1ヶ月ほどで問題の形式やテキストの文章に慣れていきましょう。
行政書士の勉強②行政法と民法を全力で勉強しよう|2ヶ月~4ヶ月
2ヶ月目からは行政書士のメイン科目である行政法&民法をやっていきましょう。
この2つの科目は行政書士の最重要科目なので、正直3ヶ月でも足りないくらいです。
というかこの2つの科目は試験日まで毎日短時間でも触っておくと良いですよ。
とにかく配点が大きすぎるので、やればやるほど点数が伸びると思います。
行政書士の勉強③一般知識を侮るな!|5ヶ月
行政書士には法律だけじゃなく一般知識という科目もあるのです。
個人情報保護法とか、政治経済歴史とか文章理解とかそういう昔のセンター試験のような問題が出てきます。
この科目の厄介なところは足切りがあるところです。
あまりに一般知識の点数が低いと例え法律科目が満点で合格点を超えていても足切りで不合格になってしまいます。
なので一般知識は絶対に侮ってはいけないし勉強しておかないといけません。
とはいえこの科目は範囲がとても広く何が出るのかよく分からないという困りもの。
なので、ある程度出題されそうなところを予想して的を絞った勉強が有効です。
- 個人情報保護法は必ず勉強する
- 政治経済は過去問を解いて受験用の参考書も軽く目を通す
- 文章理解はとにかく慣れるように
あたりに気を付けて、
行政書士の勉強④会社法も一応やっておく|6ヶ月

行政書士における会社法はなかなか厄介な存在。
範囲が膨大な割に配点が少なく、せっかく勉強したのに全然解けなかったみたいな悪夢も起こりうる科目です。
間違いなく勉強するコスパは悪い科目だと言えますが、行政書士試験は最後の1,2問正解か不正解かで合否が分かれるギリギリの人も多いので、完全に捨てるのも忍びない。
完全に捨てる派の人もいますが、僕は個人的には会社法の基礎的な部分や頻出事項を見ておけば良いと思います。
6ヶ月目は他の科目の復習もしつつ会社法の過去問をひたすら解いてよく出る部分を頭に叩き込んでください。
4択→2択に出来るだけでもだいぶ合否に影響あるので、「絞って」勉強していきましょう。
行政書士の勉強⑤全科目を復習&苦手を克服|7~10ヶ月
ここまででだいたいの範囲を勉強し終えたと思います。
でも勉強したと言ってもまだ問題はそれほど解けないし知識も定着が浅いはず。
ここから一気にスパートをかけていきます。
先程も言ったように毎日、行政法か民法は必ず触れるようにしつつ全科目を復習して回していきます。
僕は、
- 月曜日→行政法&憲法
- 火曜日→行政法&憲法
- 水曜日→民法&一般知識
- 木曜日→民法&一般知識
- 金曜日→行政法&会社法
- 土曜日→行政法&会社法
- 日曜日→民法
のようなイメージで1日2科目を目安に勉強していきました。
3科目や4科目を勉強しようとすると頭が切り替わらず進みが悪いんですよね。
「今週は民法の過去問10年分を全部解こう。」
「今日はひたすら行政法の行政事件訴訟法を勉強しよう。」
などジャンルや範囲を絞ってそこだけ一気に勉強すると知識が頭に残りやすいのでおすすめ。
行政書士の勉強⑥総復習|ラスト1ヶ月

最後の1ヶ月は今までの苦手分野を再度解いてみたり、模試を受けて実力試しをしたり、テキストを通しで読んで総復習をしたりするのがベスト。
それと同時に体調管理も意識していきましょう。
試験の日と同じ時間に起きるようにしたり、夜ふかしは止めて朝活に切り替えたりと、無理せずいきましょう。
せっかくここまで頑張ってきたのに最後に体調を崩したら悲しいですからね。
2022年1月からの行政書士勉強ロードマップ
- 2022年1月→憲法
- 2022年2月→行政法&民法
- 2022年3月→行政法&民法
- 2022年4月→行政法&民法
- 2022年5月→一般知識
- 2022年6月→会社法
- 2022年7月→全科目を復習&弱点克服
- 2022年8月→全科目を復習&弱点克服
- 2022年9月→全科目を復習&弱点克服
- 2022年10月→全科目を復習&弱点克服
- 2022年11月→総復習&体調管理
結論として、上記のように進めるのがおすすめです。
もちろん正解はこれだけじゃないので、「ここはこうした方が良いな。」と適宜カスタマイズしてくれて大丈夫。
計画通りに行くか心配な人は
自分で計画を立ててその通りに実行できる人は独学でも問題ありませんが、それが難しいという人もいますよね。
計画を立てられない、仕事をしていて忙しいなど人によって環境は様々。
「行政書士に受かりたいけど自分一人では心配。合格までの道筋を示して欲しい」
という方は通信講座に頼るのも手です。
独学よりお金はかかりますが、その分真剣に取り組むだろうし、
通信講座なので勉強のペースはある程度決めてくれるのが良いですね。
「今月までにここまでやりましょう。来月はこれをしてください。」みたいに受験のプロがナビゲートしてくれるので、右も左も分からない初心者の人には心強いサービスとなります。
以下に主要な行政書士の通信講座をまとめてみました。参考にどうぞ。

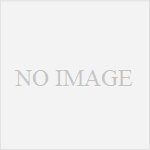
コメント